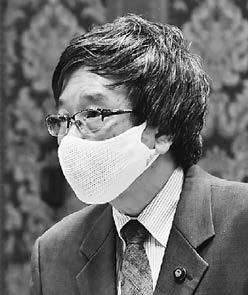���c���^��
�������I�j�N�@���ł��B
�@������@�ɂ��Ă������������Ǝv���܂����A���̑O�ɁA���̃R���i��ő�ʂɔ��s���ꂽ��������ǂ�����̂��Ƃ����_�ɂ��ĕ��������������������Ǝv���܂��B
�@�܂��A�R���i��Ƃ��Ĕ��s���ꂽ���ł��ˁA�J�E���g�̎d���A��֘A�Ȃ�ł����ˁA����Ǝv���܂����A�Ƃɂ����A�R���i�Ή��Ƃ��Ĕ��s���ꂽ���A�����Ȃ͍��ǂꂮ�炢���Ə�������Ă���܂����B
�����{�Q�l�l�i�p�c���N�j�@�������\���グ�܂��B
�@�܂��A�R���i�̂��߂ɔ��s�������Ƃ����̂�ʘg�ɂ��Ă���킯�ł͂������܂���̂ŁA���낢�덬�����Ă��܂���ł����A��̂̊�����\���グ�܂��ƁA�ߘa��N�x�̕�\�Z���ǂ��������̂��������Ƃ������Ƃ��Ǝv����ł����A�ꎟ��ł͓�\�܁E�����~�A��ł͎O�\��E�㒛�~�A�O����ł͓�\��E�l���~�ł���܂��B�����A�O����͌��łւ̑Ή��ł��Ƃ��R���i�ȊO�̕����������Ă���܂��̂ŁA���������Ƃ���̐����́A�\�������܂���A�ł��Ă���܂���ǂ��A��̂����������s���������܂��āA��N�x�Ɋւ��܂��Ă͔��\���~�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���܂��B
�@�܂��A���N�̓����\�Z�ɂ��܂��Ă��A�ܒ��~�̗\������܂߁A���낢������Ă���Ƃ������Ƃł������܂��B
�������I�j�N�@���肪�Ƃ��������܂��B
�@��N�Ԃ̗\�Z�ɂ��C�G���Ă���قǂ̃R���i�Ή��̍������s���ꂽ�Ƃ������Ƃł������܂��B���̍�������ǂ�����̂��Ƃ����̂͂��낢��l���Ȃ��Ⴂ���Ȃ����ł���܂�����ǂ��A�ʏ�̍��Ɠ����悤�ȏ��҂��l����ƁA������Ƒ�ςȂ��ƂɂȂ��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�O�̕��@���l�������ł͂Ȃ����ƁB��́A���c���悭������l�l�s�ł��ˁB���c�o�ϊw�A���ȏ��ɏ����Ă��Ȃ����E�ł������܂����A�܂����v���ƁA�؋��������Ă����Ƃ������E����B������́A���łł����Ԃ��Ă����Ƃ����̂���ڂł��ˁB�O�ڂ́A�䂪�}�͂��̊Ԃ���������Ă������Ă�����Ă��܂�����ǂ��A�ʉ�v�A���ʉ�v�A�ʊ���ɂ��āA�ʌ��Ă̒������҂̍��ŁA���Ղɑ��łɂ��Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB
�@���̎O����̍l����������ł͂Ȃ����Ǝv����ł�����ǂ��A����A���̗\�Z�ψ���̌�����ō������Z�̐��Ƃ̕�����l�ɕ����܂�����A����l�Ƃ��䂪�}�Ɠ����A�ʉ�v�A���ʉ�v�őΉ�����̂���Ԃ�����ł͂Ȃ����Ƃ����ӂ��ɁA�������������������������Ă���܂����A����������b�̂��l���͂������ł��傤���B
��������b�i�������Y�N�j�@�肽�����ǂ�����ĕԂ����Ƃ������̘b�Ȃ�ł�����ǂ��A���̓��ʉ�v�ɂ��܂��ẮA�����䑶���̂悤�ɁA����͍����@�̒��œ���̂�����Γ��������ē���̍Ώo�ɏ[�Ă�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���܂��̂ŁA��ʉ�v�Ƃ������A���̍Ώo�Ƌ敪���Đ���������K�v������ꍇ�ȂǂɌ����Ă���͐ݒu������̂Ƃ���Ă���܂��B����͌䑶���̂Ƃ���ł��B
�@���������܂��āA���̐V�^�R���i�֘A�̗\�Z�ɂ��܂��ẮA���̓��k�̂Ƃ��̕������ʂ̗\�Z�ƁA�֘A�̓��ʗ\�Z�Ƃ͈قȂ��āA�����[�u�̊m�ۂ����ɍu�����Ă���킯�ł͂���܂���̂ŁA���������܂��āA�܂��A���̋�̓I�Ȃ����������̂����Ƃ������ʂ����Ȃ��܂܂ɂ������������Ƃ����܂��ƁA���ʉ�v�Ƃ����̂̐ݒu�����Ƃ����̂͂�����ƐT�d�ɂ��Ȃ����ʂ��낤�ȂƁA��������͂����v���Ă���܂��B
�@�܂��A�������܂����悤�ɁA���̐V�^�R���i�ɂ��܂��āA��\���A�S���ɋ߂��悤�ȗ\�Z�Ƃ������̂������o�Ă���ƁA�����Ȃ��̂�˂����킹�܂��Ƃ����Ƃق��̂Ƃ���ɉB��ē����Ă���Ƃ��날��̂�������܂��A�����̍������������Ă��邱�Ƃ͂��������ł���܂�����A�����������Ӗ��ł́A���̍����̐M�F�Ƃ������̂������Ȃ��悤�ɂ��Ă����܂���ƁA���Ȃ��Ƃ��}�[�P�b�g�̐M���Ƃ������̂������Ƃ����̂͂���ł����낵����ŁA�����Đ��A�o�ύĐ��A�������������̗̂����Ƃ����̂�}���Ď��̐���Ɋm���ɂȂ��ł����Ƃ����̂���X�̐ӔC���Ǝv���Ă���܂��B
�@������A��X�̏ꍇ�́A���Ƃ����Ă����̏��q����Ƃ����A������Ƌɒ[�ɂق��̍��ɔ�ׂĐi��ł�������肪����܂��B�����������̂��l���܂��āA���ǂ��Ƃ��ẮA�������������̂̂���͒n���ł͂���܂�����ǂ������ɂ���Ă����A���ꂵ���ق��ɁA���̂Ƃ���A���ʂɂ���Ƃ��������āA�ς��ƈꊇ�œ����߂Ƃ������Șb�悭���Ă��������������Ⴂ�܂�����ǂ��A���ǂ��Ƃ��Ă͍��������������Ƃ��l���Ă���킯�ł͂������܂���B
�������I�j�N�@���ʂ��������A�ς��Ɠ������o�Ȃ����z�ł���܂��̂ŁA�����A�����Ȃ͂������łƂ����̂��O���ɒu�������ł�����ǁA����͑�ρA�������Ď��Ԃ�����������Ƃ����\��������܂��̂ŁA���ꂩ��̋c�_�ł������܂�����ǁA�T�d�Ɍ������Ă����ׂ��ł͂Ȃ����Ɛ\���グ�Ă����܂��B
�@������@�ł�����ǁA��قǂ̖q�R�Ђ낦�c�����炲�����܂����̂ŁA�قړ��������������Ɨp�ӂ��Ă����W�ŁA���X�ق��̂��Ƃ����킯�ɂ������܂���̂ŁA�����ɂ͂Ȃ�܂�����ǁA������Ƃ������蕷���Ă��������ȂƎv���܂��B
�@�����\�N���炢�O�ł��ˁA�����̍������Z�ψ���ő�c�_�ɂȂ�܂�������ǂ��A�����قڂ����Y�ꂩ���Ă���܂��̂ŁA�������Z�̒������ɓ����̋c���^�Ń|�C���g�ɂȂ���̂����Ă�����āA���̍X�ɔ����������̂����茳�ɁA�c���^�̔�����p�ӂ��Ă������܂��B
�@���ꌩ�Ȃ���A�����������̂��A�ǂ��������ꂾ�����̂��A������Ƃ܂��m�F�����Ă��������Ǝv����ł����ǁA���߂āA�܂�������\�l�N�A��Z���N�x�̓�����@�A�܂蕡���N�x�̒�Ă����ꂽ�A�������ꂽ�ƁB���̂Ƃ��̓�����@�̎�|���A�����̎�|���܂��Ȍ��ɏq�ׂĂ������������Ǝv���܂��B
�����{�Q�l�l�i�p�c���N�j�@�������\���グ�܂��B
�@������̔����ł��Ƈ@�ƇA�̂Ƃ���Ɋւ��킯�ł������܂�����ǂ��A������\�l�N�����͗\�Z�̐���������̗��t���ƂȂ������@���������Ȃ����߁A�n���s�����܂߁A���������ɉe�����y�ڂ����˂Ȃ����������Ƃ���ł������܂��B
�@�����������ŁA�����̖�c��������A�ǂ̐��}������������Ă����ʂ͓�����s������Ȃ��ł��邱�Ƃ���A������\�l�N�x�̑Ή������łȂ�����ȍ~���l���āA�\�Z�Ɠ�����@����̓I�ɏ������郋�[�������ׂ��Ƃ������Ăт����������āA�����̖���}�A�����}�A�����}�̎O�}�̊ԂŌ�c�_������A�O�}�m�F���ɂ����ĕ����N�x�ɂ킽�������̔��s���\�Ƃ��錻�݂̘g�g�݂����܂Ƃ߂�ꂽ�Ƃ���Ə��m�������Ă���܂��B
�������I�j�N�@���̋c���^�ł����A�����̖�c����������ꂽ���Ƃ��J��Ԃ��������ꂽ�킯�ł���܂��B�v����ɁA�˂��ꍑ������킯�ł���܂��B����͂悭�F����A����͊o���Ă���������Ǝv���܂��B
�@�Q�c�@�Ŗ�}�������ɂȂ�܂��ƁA�\�Z�͏O�c�@�ʼn�����ΏO�c�@�̗D�z�Ŏ���������Βʂ�܂�����ǂ��A���@�Ă͂����͂����Ȃ��Ƃ������ƂŁA�Q�c�@�œ����̖���}�������ɂȂꎩ���}�������ɂȂ�A�ǂ���ł����Ă��Ȃ��Ȃ��ʂ�ɂ��������܂�Ă���Ƃ����Ƃ���ŁA����I�ȍ����^�c�Ƃ����̂́A�܂肻�̂˂���ɂ���č��E����Ȃ��Ƃ����Ӗ����Ǝv���܂����A�����N�x�̔��s��F�߂�Ƃ������ƂŁA�������̍��ӂł��ꂽ�킯�ł��ˁB�v����ɁA�˂���Ή��ȊO�̉����ł��Ȃ������킯�ł��B�˂��ꂪ�Ȃ������炱�������@�Ă͏o�Ă��Ȃ������킯�ł��ˁB����́A���������������������c���̊F����݂͂�Ȍ䑶���̂��Ƃ��Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B
�@����A�Ȃ��l�N�ԂƂ����̂������̋c���^�ɏo�Ă���܂����A��قǖq�R�c��������w�E�������܂����B�v����ɁA������@�̑�O���Ƃ����̂��������܂��āA���̕����N�x�Ŕ��s����Ƃ����A�ŁA�ꊇ�������̂�����ǂ��A������Ƃ����āA���̔��s�͗}���I�ɂȂ�Ȃ�������Ȃ��ƁA�l�N�ԂƂ�����������Ƃ����Ď��R�ɂ������ʖڂ�ƁA���̔��s�͗}�����Ȃ�����Ƃ���������@�̎O��������܂������̂ł�����A�����S�ۂ��邽�߂ɁA����ɉ����邽�߂ɁA����́A�O�}���ӂŊm�F���ꂽ�������S���v��ł��ˁB
�@��قǂ������܂������A�v���C�}���[�o�����X�A�f�c�o��ł����ǁA�̐Ԏ�������ڕW�A���̖ڕW����Z��ܔN�ƂȂ��Ă������̂ł�����A���̂Ƃ��̓������������Z��ܔN�ɍ��킹�Ďl�N�ԂƂ����Ƃ������Ƃł������܂��āA�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́A�����̋c�_�͂˂��ꂪ�A�˂��ꍑ��ł��낢�날�����ƁA����ς����I�ɗ\�Z�͎��s���Ȃ��ƍ����ɂ����f�|����Ƃ����悤�ȗ��R���������킯�ł��ˁA�F����B�������A���Ƃ����āA�ܔN�ԁA�l�N�ԁA�킠���Ƃ����R�c���Ȃ�����Ƃ����đ��₵���Ⴂ���Ȃ��ƁA������A������@�̎O����S�ۂ���Ɨv���������č��������v���C�}���[�o�����X�Ƃ̊W�����߂�ꂽ�킯�ł���܂��āA����A�悭�o���Ă����K�v�����邩�Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B
�@��Z��Z�N�ł�����ǂ��A�܂��A�����͖���������b�ł������܂������炨������������ł����ǁA�˂���͂����������Ă���܂����B���̖@�Ă͂��������˂����ł������܂����B�˂��ꂪ�������Ă����ɂ�������炸�A�Ȃ���Z��Z�N�ɂ��ꂪ�������ꂽ��ł��傤���B
��������b�i�������Y�N�j�@���̓�����@�ɂ��ẮA�������܂����悤�ɁA��������Z��l�N�ɁA�����̖���}�A�����}�A�����}�̊m�F�����X�ŁA�O�}�ŋc���C���ɂ���ĕ����N�x�ɂ킽�������s�\�Ƃ���g�g�݂��ł�����ł����A���A���搶��w�E�̂Ƃ���A������\���N�̉����ł́A���Ȃ��Ƃ�����ܔN�Ԃ͂��̓�����s������Ȃ��ł��낤�Ƃ���������������Ԃɂ��钆�ŁA�O�}�ł����߂����������g�g�݂Ƃ������̂��A������������I�ȍ����^�c���m�ۂ���Ƃ����ϓ_����A���N�x�܂łł����A�ܔN�ԁA������̔��s���������������Ƃ����悤�Ɍ䗝������������Ƒ����܂��B
�������I�j�N�@�v����ɁA���̂����t���̂܂��ƁA�������������^�c�̈���Ƃ������Ƃ́A�˂���͉�����������ǂ��A�܂������˂��ꂪ�������邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃ��܂܂�Ă���킯�ł��傤���B
��������b�i�������Y�N�j�@�\���ɂ���Ǝv���܂��B�Ȃ����Ƃ����҂͂��܂����ǁA���蓾��Ǝv���Ă��܂��B
�������I�j�N�@�ߋ��ɂ����j�I�Ɍ����˂���݂����Ȃ��Ƃ��������킯�ł�����ǂ��A�˂��ꂪ���邩��Ƃ������ƂɂȂ�܂��ƁA��������������������@�㋁�߂��Ă������Ƃ��炢���ƁA�˂��ꂪ���邩�炸���Ƃ��������Ⴈ���Ƃ������ƂɂȂ�ƁA������ƍ����@�Ƃ̊W���^�킵���Ȃ��Ă���ƁB
�@�ł�����A���́A���������˂��ꂪ�A���X�˂���Ή��Ŏn�܂��āA�˂��ꂪ�����Č����I�Ȗ��Ƃ��Ă��낢�날��������A��肠���������ܔN�Ԃ͂Ƃ������ƂŁA���ǂ��͔����܂������ǒʂ����ȂƎv���Ă��܂������ǁA�������ꂽ��������邩������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���������Ƃ��̗��R�����Ă��Ă��܂���ł͂Ȃ����Ƃ����ӂ��Ɏv���܂����A������A��Z��Z�N�ł��ˁA���̂Ƃ��͌ܔN�ł���ˁA�ܔN�Ԃł���ˁB���̌ܔN�Ԃ̗��R���A��قǖq�R����Ƃ̋c�_�ł���܂�������ǁA�v���C�}���[�o�����X�A���x�̓v���C�}���[�o�����X�̍������ł��ˁA�������Ƃ������{�����̍������S���ڕW�̔N�x�ƍ��킹���Ƃ������Ƃł��ˁB
�@�������قǐ\���グ�܂������A���̂Ƃ��܂ł͓�����@�̎O���̌��̔��s�̗}���ɓw�߂�Ƃ������Ƃ���Ɍ��i�Ɉӎ�����āA�ꉞ�ł��ˁA�ꉞ�ӎ�����āA���ѕt�����ČܔN�Ԃ������Ƃ����ӂ��Ɏv���킯�ł��ˁB
�@�����������Ƃ������Ǝv����ł����A����͂�낵���ł����B
�����{�Q�l�l�i�p�c���N�j�@�����́A�ŏ��̓�\�l�N�̂Ƃ��ɁA���N�ɂ����炢�����Ƃ�����肪���炭�Y�܂��������낤�Ǝv���܂�����ǂ��A���̂Ƃ��A��c��������̂��Ăт����́A���̋L�҃��N�Ȃ��������A��Z��Z�N�A��Z��Z�N�܂ł̍������A�������Z��Z�Ƃ����l���������邵�A�����̓�Z��܂܂łƂ����l����������Ƃ������Ƃł��Ăт����������āA���̂Ƃ��A���ۂɉ��N�ɂ����炢�����Ƃ����Ƃ��ɁA�������ɋ�N�͒����Ƒ������l���ɂȂ����̂ŁA��Z��ܔN�A�l�N�Ő�ꂽ�Ƃ������Ƃ��Ƃ����ӂ��ɉ�X�Ƃ��Ă͎~�߂Ă���܂��B
�@���������āA���������ނˎl�N���x�Ƃ������Ƃł���A�c���Ԃ��ܔN�ł������܂��̂ŁA���̍ŏI�S�[���̍������A��Z��Z�N�x�܂ł̌ܔN�Ԃɂ��Ď��������肢�����Ƃ����o�܂ł������܂��B
�������I�j�N�@����A������ƈႢ�܂���B���̂Ƃ��͎�������ŋc�_�A�悭�o���Ă��܂����A��Z��Z�N�ł�����B�����ɂ͖�����b�̋c���^�A�䓚�ق���܂����A�ق��ɂ�����܂��āA�v����ɁA���낢�낶��Ȃ��āA�v���C�}���[�o�����X�̍������Ƃ̊W���Ƃ������Ƃق��J��Ԃ�����Ă���܂���ŁA������Ƃڂ₩�������������Ă��炤�Ɠ����̍���c�_�͉��������̂��ƁA���ق����������̂��ƂȂ�܂��̂ŁA����͂������炩�ɁA������b�̌䓚�فA�����̌䓚�قɂ�����Ƃ���A�v���C�}���[�o�����X�̍������Ƃ̊W���������Ƃ����̂́A����͂����������Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B
�@���̏�ŁA����̉����̎�|�����߂Ă�����Ɛ������Ă���܂����B
�����{�Q�l�l�i�p�c���N�j�@�܂��A������\�l�N�ɎO�}�m�F���Ƌc���C���ɂ���Ē�߂�ꂽ�g�g�݂��p���A��������������s������Ȃ������������ɂ��钆�ŁA����I�ȍ����^�c���m�ۂ���ϓ_����A���s�@�Ɠ��l�ɍ���ܔN�Ԃ̓�����̔��s�̍��������߂���̂ł������܂��B
�������I�j�N�@�Ȃ��܂����x�̓v���C�}���[�o�����X�A���́A�����Ɍ����āA�������x�̓v���C�}���[�o�����X�Ƃ��������ѕt����ɂ͂�����ƌ����߂���A���ƁA����͂悭�������ł���B�������A���܂ł͓�����@�̎O���Ƃ̊W�����i�ɂ��Ă����Ƃ����W�ł����ƁA���ۂ��Ɣ����Ă���ƁB���R�ƌܔN�A�������S���̌ܔN�ƁA���ꂾ���Ƃ����Ƃ���́A���Ƃ����̂��A������ƁA�_���I�ȍ��܂Őςݏd�˂Ă������̂��炩�Ȃ��Ă���Ƃ����ӂ��Ɏv����ł�����ǂ��B
�@��قǁA��������b���A��������Ǝ����\���グ�������I�Șb�ŁA�v���C�}���[�o�����X�Ɠ�������s�̊����Ƃ���v������̂͂��������I�ɓ���ƁA�͂����茾���āB�������Ȃ��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������āA�v���C�}���[�o�����X�Ƃ̊W�͍��ѕt���Ă��Ȃ���ł��Ƃ����䓚�ق���܂������ǁA����͂�����̌����_�Ƃ��ĕ�����Ȃ��͂Ȃ���ł�����ǂ��A�����������Ƃ���Ȃ������ł����A�������́B
������b�i���������N�j�@��قǖq�R�搶����̎���̂Ƃ��ɂ����������̂́A�����I�ɓ������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āA�v���C�}���[�o�����X�̐��{�ڕW���炷��ƁA��Z�ꔪ�N�Ɉ��ύX���ꂽ���Ƃ�����܂��ƁB��Z��Z�N�x�̍������ڕW����Z��ܔN�x�ɕς���Ă��܂�����ǂ��A���X�̌��s�@���ς���Ă���킯�ł͂Ȃ��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ���\���グ���̂ƁA������́A���̔��s���ԂƂ��ꂩ��v���C�}���[�o�����X�̍������Ƃ����͈̂�v������_���I�K�R���͂Ȃ��ƁB�Ƃ����̂́A�v���C�}���[�o�����X�̍�������B�����Ă��A������͔��s�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����炾�ƁB����܂ł̗ݐύ�������܂�����A����ɑΉ�����K�v������ƁB���̓�_��\���グ�܂����B
�������I�j�N�@��������A�������ł����s�������Ȃ��Ă����Ƃ��A�N�������v���Ă��Ȃ��ł���B�����Ƒ�������Ȃ��Ǝv���A��}������������ꍇ�ł��B����͂��������������ƁB���́A�ܔN�X�ɉ������܂��Ƃ��A���̈Ӗ��Ȃ�ł��ˁB
�@����́A����ς荡�܂Ō��i�Ɍ��ѕt����ꂽ���A�����ăv���C�}���[�o�����X�����Ƃ͌���Ȃ��āA���܂��܃v���C�}���[�o�����X���������̂ŁA�O�}���ӂ̏ꍇ���A���{�������������̂ŁA����ƌ��ѕt���Ă���܂����A������ɂ���A���炩�̂���������̓I�ȍ������S�ڕW�ƁA���̌ܔN�ԂƂ����N�ԂƂ����̂͂�������������������ׂ��ł͂Ȃ����ƁB�����łȂ���A�ʂɌܔN����Ȃ��Ă������킯�ł���ˁB�O�N�ł��������A���N�ł��������Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��ˁB
�@���������Ӗ��ŁA���̌ܔN�̍������q�R����������悭������Ȃ��ƁA�����������Ƃ��Ǝv����ł����A������Ȃ���ł����ǁB
������b�i���������N�j�@�l�N�Ȃ̂��A�ܔN�Ȃ̂��A�Z�N�Ȃ̂��A����A��N�A�O�N�Ȃ̂��A���낢��ȑI����������낤�Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B���߂͎l�N�A�����đO��ܔN�Ƃ������Ƃŗ��܂����B����͑O��P�����Ă����������Ƃ������Ƃł���܂��B
�������I�j�N�@�ł�����A�O��͂���������̓I�ȍ������S���ڕW�A���܂��܃v���C�}���[�o�����X�Ƃ�����������������ł����ǁA���ꂪ��������ł��B������A�O��P����Ƃ����ƁA���P���Ă��Ȃ��Ǝv����ł���A�ܔN�Ԃ̍����ɂ��ĂˁB������\���グ�Ă���킯�ł������܂�����ǁB
�@������Ƃ悭������Ȃ���ł����ǁA�����̇D�̋c�_�ł����ǁA���N�̓�\�l���A�O�c�@�̍������Z�ψ���ŁA��v�ǎ�������ł��ˁA�v����ɂ��������c�_����������ł��傤�ˁB��قǂ̌J��Ԃ��ɂȂ�܂�����ǂ��A����I�ȍ����^�c���m�ۂ���ϓ_����A����������J��Ԃ������Ă���ƁB���̓_�ɂ��܂��ẮA���ɐ����I�Ȃ��b�ɂȂ�܂��̂ŁA��������ȏ�\���グ��͍̂����T���܂��ƁB
�@���̐����I�Ȃ��b���āA�ǂ��������ƂȂ�ł����ˁB
�����{�Q�l�l�i�p�c���N�j�@����́A�Ăт˂���ɂȂ����Ƃ��ɂ��A�����ƁA�ʂɂ킴�킴�l���Ɏ��悤�Ȃ��Ƃ͂��܂����Ƃ�����|�̖�}�̈ψ�����̌�w�E������A����ɑ��č�����b����A�܂��A�����͂����Ă��˂���Ƃ����̂͂Ȃ��Ȃ���������͂��ł���Ƃ������Ƃ����̑O�̒i�K�Ō�c�_������܂��āA�������̂ł͂��낤�Ǝv���܂����ǎ����Ƃ������y����悤�Șb����Ȃ��Ǝv���܂����̂ŁA�����͍����T�������Ă����������Ƃ������Ƃł������܂��B
�������I�j�N�@��������ƁA�ܔN�ɗ]�荪�����Ȃ��Ƃ����̂́A���������Ⴂ���Ȃ���ł����ǁA������܂������ǁB
�@��������ƁA���������Ă��ꂩ��A���̓�������s�́A�����I�ɒN������Ă����ꂩ�炸���Ƒ������낤�Ƃ����͕̂�����킯�ł����ǁA���̓�����@���ܔN��܂���������邩������Ȃ��B���������Ƃ��ɁA����͂����������S�������f����Γ�����@�̎O�������Ă���Ƃ����ӂ��ɂ����Ⴆ�A�������Ƃ�����ł����A�������ƁA�������Ƃ���͒�Ăł��Ă��܂��A��Ă��邱�Ƃ͉\�ɂȂ�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����悯��B
�����{�Q�l�l�i�p�c���N�j�@��肠�����A���̕�����B
�@����̑Ή��Ƃ��Ă��̂悤�ɒ�Ă������Ă����������Ƃ������ƂŁA�ܔN��ɂ��Ă͉����\�f�������ĂƂ������Ƃł͂������܂���Ƃ������Ƃ�\���グ�Ă��������Ǝv���܂��B
������b�i���������N�j�@��قǑ��ψ�������������܂�������ǂ��A������Ŏ�������邱�ƂƂ����̂́A�����A�Ԏ����s�ł��邩�ǂ����Ƃ������̗L���̘b�ł���܂��B���A�����܂��čl����ƁA�Ԏ����s���Ȃ��Ƃ������Ƃ͑S���A�ꉭ�~�ł����s���邽�߂ɂ͂��̓�����Ŏ�������Ȃ��Ⴂ���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B
�@���͍������S���̊��͍����f���Ă����ׂ����Ǝv���܂����A���̒��Ŋ̗v�Ȃ̂́A���̔��s�̗L���Ƃ������Ƃ����A���s���z���ǂ������ӂ��Ƀ}�l�[�W���Ă����̂��A�}�����Ă����̂��Ƃ������Ƃ���Ȃ����Ǝv���܂��B������̋c�_�Ƃ����̂͋ɂ߂ďd�v���Ǝv���܂�����ǂ��A����ȊO�̘g�g�݂Ƃ����̂��K�v�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ���Ȃ����Ǝv���܂��B
�@���̒��ŋ��z�ɂ��Č����ƁA��͂��ԑ厖�Ȃ̂͗\�Z�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B���{�E�^�}���ǂ̂悤�ȗ\�Z�Ґ��̍l���������ė\�Z���o���Ă���̂��A�����č���ŗ\�Z�R�c�ɂ����Ăǂ�����ă`�F�b�N���Ă����̂��A���ꂪ������`�I�ɂ͈�ԏd�v�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ���Ȃ����Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B
�������I�j�N�@����͂܂��ʂ̋c�_�ł��ˁA���z�A���s�̊z�́B�ʂ̋c�_�Ƃ����܂����A����͓�����O�̋c�_�ł���܂��āB
�@����̂��̌ܔN�ԂƂ��A���܂ŁA���x���J��Ԃ��悤�ł����ǁA�l�N�ɂ͈Ӗ��������Ďl�N�ԁB���̊Ԃ͌��̔��s�̗}���ɓw�߂܂��ƁA���̒S�ۂƂ��ăv���C�}���[�o�����X�������Ă����B�ܔN�������ł����ˁB����͂��ꂪ�Ȃ��Ƃ����Ƃ���ŁA���R���̊z���厖�ł���ˁA���s�z���ˁB�����ǁA���̓�����ܔN�ԂƂ���v����ɍ���ŋc�_���Ȃ��ŁA�R�c���Ȃ��łۂ�ƔF�߂Ă����Ƃ��������ł���ˁA����ɂ��č��c�_���Ă���킯�ł���܂��̂ŁB
�@���Ƃ����܂����A������Ƒ傫���U��Ԃ�܂��ƁA���������˂����Ƃ������R�͂Ȃ��Ȃ����ƁA�v���C�}���[�o�����X�ȂNj�̓I�ȖڕW�ƌ��ѕt���邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ��āA��ʓI�ȍ������S���A�����i���̃e�[�}�̂悤�ȁA�i���̃e�[�}�̂悤�ȖڕW�ɂȂ����ƁB����œ�����܂��ܔN���s����Ƃ������ƂɂȂ�܂��ƁA���x�͖�����b�̂��l����������ł����ǁA���������A�����������ƂɂȂ������ł��A���������N�ԂƁA�ܔN�Ƃ������R���A�O���ܔN���������獡�x���ܔN�݂����Șb�ŁA���̍������Ȃ������Ɖ����ł���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂���Ȃ����Ǝv���܂����A������b�͂��������l���ł����B
������b�i���������N�j�@��b�̑O�ɁB
�@����ܔN�ԂƂ����̂͑S���������Ȃ��Ƃ������Ƃł͂���܂���B����̖@�Ă̏����Ԃ�Ƃ����̂́A�v���C�}���[�o�����X�̍������Ƃ����͓̂���Ă��܂���ǂ��A���{�Ƃ��Ă͓�Z��ܔN�������Ƃ����͖̂ڕW�Ƃ��Č������Ă���܂��̂ŁA���̈Ӗ��œ��P�����Ă����������Ƃ������Ƃł������܂��B
��������b�i�������Y�N�j�@���A��������b�̕����瓚�ق����ɂ����Ă���܂�������ǂ��A���ꍡ���ƂȂ��Ŏ������ꂾ���A�Z�\���̂͂����Z�\�����S�R�͂����Ƃ����悤�Șb�ɂȂ��Ă���ƁA���������Ă���Ƃ����A�����Ƒ����悤�Ȋ��������܂����ǁA���̒��͂���������Ƃ͌���ʂ̂ŁA�ԈႢ�Ȃ��ǂ��Ȃ�ƁA�ǂ��Ȃ���ɂ��낢�낸���Ɨǂ��Ȃ��Ă����悤�Ȋ�����������̂Ȃ̂ŁA�Ȃ��Ȃ��オ�����艺��������Ƃ����͕̂t�������Ƃ����̂͂��̎l�\�N�Ԃ����ɂ��Ă��Â������v���܂�����ǂ��B
�@����̂Ƃ����A���Ȃ��Ƃ��A���̃R���i�̌�A�o�ςƂ����͉̂O���ɉ��ɏ���Ă����܂��ƁA���Ȃ��Ƃ����ǂ��Ƃ��Ă͂����������悤�Ȗ������Ȃ��Ă������悤�ȏɂȂ��Ă���\��������ƁA����[�����Ⴀ��܂���̂ŁA�܂��A�����������̂��Ǝv���ĉ�X����\���N�܂łƂ����̂���肽���Ǝv���Ă���܂��B
�@������ɂ��Ă��A������������X�A���̌ォ��ܔN�����Ƃ��A�ǂ����������ɂȂ��Ă��邩�Ƃ����̂͂悭������܂���ǂ��A�������A���ǂ��Ƃ��ẮA�����������悤�Șb�ł������܂����R�̂��Ƃ��ܔN�ԂƂ��������Ȃ�Ƃ����b�����ՂɎ����o�����Ƃ��Ȃ��悤�ȓw�͂����ǂ��͍����ȂƂ��Ă͂��ɂႢ���ʂƁA���{�Ƃ��Ă͂��Ȃ����Ⴂ���ʂƂ��낾�ƁA��{�I�ɂ͂����v���Ă���܂��B
�������I�j�N�@����������w�͂Ƃ������Ƃ��͓�����O�ɕ������ł����ǁA����A������ƕ������ς��܂����ǁA���f���Ă��A���̗��@�����Ƃ����܂����A�ܔN�ɂ���A�ܔN�ԂƂ����A���@�����Ƃ��������R��������Ȃ���ł����ǁA����Ȃ����N�c�_�����Ⴂ���Ȃ���ł����B�Ȃ����N���̓�����@�ɂ��ċc�_���Ă͂����Ȃ���ł����B���N�c�_�������ē������ӎ��ł���Ǝv����ł����ǁA�Ȃ����N�����Ⴂ���Ȃ���ł����B
������b�i���������N�j�@���ψ�����Z���N�����̋c�_����قǕ~�����Ă��������܂����B
�@��͂�A��Z���N�����ɂł͂Ȃ��Ė��N�x�A�˂��ꂪ�������Ƃ��ɂ́A�O���ɂȂ�ƁA�\�Z�𐬗������邽�߂ɂ��̓�����@������ΐl���ɂȂ��Ă���悤�Ȍ`�łȂ��Ȃ��c�_���i�܂Ȃ��Ƃ������Ƃ��������Ǝv���܂��B�����āA���ۂɁA��Z���N�͂�����Љ�ꂽ�Ƃ�����ۂɒʂ�Ȃ��ŁA�n����t�łȂǂ���t����Ȃ��Ƃ������ƂŔ��N�Ԃ��邸��ƍs���āA���������Ɏx�Ⴊ�N���������Ƃ������Ƃ������Ǝv���܂��B
�@�ł�����A���������Ɏx��͖�����ɂ��N�����Ȃ��悤�ɂƁA���������ӎ��̉��A���Ƃŕ����N�x���Ƃ������Ƃ��������Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�������I�j�N�@�������̂Ƃ��v���o���܂����ǁA��}�������ȑΉ����������Ǝv����ł�����ǁA�\�Z���ʂ��āA�Q�c�@�͎Q�c�@�̖��ӂ����f���Ă��邩��Ƃ������Ƃ������āA����͂����{���ɐ����̋�ɂ��悤�Ǝv���ł���Ƃ����̂͂��邩��������܂���ǁA�����������Ƃ���z�肷���Ȃ��āA����ς�^��}�ł������Ƃ����c�_��������������ɂ��Ȃ�Ȃ������\��������Ǝv����ł���ˁB
�@�厖�Ȃ��Ƃ́A����ς荡�̂��̖c��ȍ����ǂ����邩�A���ꂩ��ǂꂾ�����s��}���Ăǂ�����Ă�肭������邩�Ƃ����^���ȋc�_��^��}�ł�邱�Ƃ��厖�ŁA�������������̋�ɂ���邩��Ƃ����Ă����x�����ĉ��N�����N���Ƃ����̂́A������Ƃ���A���������A����̂��̂����ɂ���鍑��ŁA����̃`�F�b�N�@�\�������邵�A�R�c����������Ƃ������ƂɂȂ�܂��̂ŁA������Ƃ����������̗��ĕ����Ⴄ�̂��ȂƎv�����肢�����܂��B
�@�Ō�̎����ɁA���ƒ����A�����́A��������̋c���^���ڂ��Ă���܂����A���͓�Z���N�̏\�ꌎ�\�ܓ��A�����������Ƃ�\���グ�܂����B
�@���́A����������Ƃ����ƁA���������Ⴈ���ƁA���ꂩ�炾��P�v�@�I�ɂȂ��Ă���Ƃ������O�������w�E���Ă��������Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��ƁB�܂��ɍ����̎��Ԃ�\�����������������Ă�������Ǝv���Ă���܂����ǁA�������A���̂Ƃ��ł��s����������ꂽ�̂͒�����������ł��ˁB
�@��������A�����������ł���ˁA�v���C�}���[�o�����X������������Ƃ�������������Ƃ����悤������ǂ��ƁA�X�ɋl�߂āA�������ꂪ�r���ł��܂������Ȃ�������A���̎l�N�Ԃ̔��s��F�߂�[�u�����������Ƃ�����̂��ƁA�悭�����܂ŋl�߂�ꂽ�ȂƎv���܂����ǁB���������A���������c�_��������ł���A���̂Ƃ��́B���������c�_��������ł��ˁB
�@�����������̂������Ɖ����B���ɂȂ��āA�����Ƃ����b�ɂȂ��Ă����ł����ǁA�܂��A���������āA����ς�ꌾ�����܂����ˁB
�@���̂Ƃ��̋c�_�͂������ł����B
������b�i���������N�j�@�s���ƌ����Ă��������܂��āA�ǂ������肪�Ƃ��������܂��B���ψ��ɂ��̂悤�Ɍ����Ă��������A��ϗL���Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B
�@���̏�ŁA��قǖq�R�搶�̎���̂Ƃ��ɂ��\���グ����ł�����ǂ��A���炩�̍������S���̐��l�ڕW�ƌ��̔��s�Ƃ����̂������N����Ƃ������Ƃ͂��蓾�ׂ����Ƃ����ӂ��Ɏ��͌l�I�Ɏv���Ă���܂��B���ꂪ���܂ł̓�������Ɠw�͋`���Ƃ����`�Ńv���C�}���[�o�����X�ƌ��ѕt���Ă����Ƃ������Ƃł���܂�����ǂ��A�X�ɂ����ƌ��i������Ƃ������Ƃ����蓾�邾�낤�Ǝ��͌l�I�Ɏv���Ă��܂��B
�@�����A���i������Ώ_��Ƃ̃g���[�h�I�t���N����Ƃ������Ƃ��낤�Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B�ǂ�����d�����邩�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�ȏ�ł��B
�������I�j�N�@�܂������������s�Ȃ��ɍ����^�c�������s���Ȃ��݂̂͂�ȕ������Ă���ƁB���̏�ŁA�����炱���A����ς�c�_�����ׂ����ƁA�c�_���瓦����ƌ�������Ȃ�ł�����ǂ��A�c�_���Ȃ���Ȃ��āA�����炱���c�_���āA�^��}�ŋc�_���āA���̂�����̖������ƁB����ς荑��̃`�F�b�N�@�\�Ƃ��R�c���̂��ƍl���܂��ƁA����ς肱�����������͈Ⴄ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ�\���グ�āA������I���܂��B
�@���肪�Ƃ��������܂����B