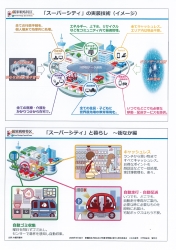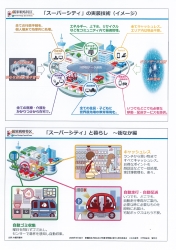
<議事録>
○大門実紀史君 大門です。お疲れさまでございます。
午前中、片山さつき前大臣が来ておられましたけど、自分だけしゃべってどこかに行ってしまいました。前大臣でこの最初の提案まとめた方ですから、皆さんの議論をしっかり聞いてほしかったんですけれども、ああいう方なのかなと思いますけど。
前回の質疑で、最先端技術を利活用した新しい町づくりというのは誰も否定しないと。便利で快適、多くの方が望んでいるのではないかと思いますけれど、ただし、今回の丸ごと未来都市、この丸ごとの意味なんですね。個人データを丸ごと管理して、丸ごとサービスをやろうということなんですけど、それは前回指摘させていただいたように、今や監視社会と表裏一体になっているということで、便利になればなるほど監視が強まるというような、最先端技術の関係ではそういう社会になってきております。
前回は歴史学者のハラリさんの見解も引用しながら、今回、資料の、前回申し上げたかったことを簡潔にまとめたのが見付かりましたので資料にも付けてあります、ハラリさんの見解ですね。また、ベストセラーになりました「監視社会」を書いたデイヴィッド・ライアンさんの新しい近著の「監視文化の誕生」についても抜粋、抜き書きをして載っけてあります。これは、是非大臣や村上さんに読んでほしいと思ってわざわざ抜き書きしたので、是非教養を高めてほしいなと思うわけでございます。一番読んでほしいのが片山さんなんですけど。
何が問題かといいますと、データが、今でもありますけど、サービスごとに、分野ごとに集積されるということ、今もあるわけですね。例えば医療ですよね。お医者さんに通う、患者さんが通う、その方の医療データは当然病院が持っていますよね。で、提供しますよね。サービス、医療サービスを受けるわけですね。今だってそれはあるわけですね、同意して。それに例えば顔認証が加わって、病院に入るときはもう診察券を入れたりしなくて顔認証で入れて、待ち時間分かるとか、スマホに来るとかね。個別のことでいえば、顔認証も含めて同意をしてということはあり得ると思うんですよね。
ところが、今回は丸ごとと、丸ごとなんですよね。例えば、私でいえば、お医者さんに行くこともあればアマゾンで本を買うこともあれば市役所に行くとか、それぞれのデータを提供していますよね。アマゾンなら本買うためにクレジットカードを登録して、住所も分かりますよね。それぞれやっているけど、それを丸ごと、丸ごとまとめられることが問題だということを指摘しているわけであります。
その個人情報が一点に集約されてビッグデータになって、ビッグデータとして分析されてプロファイリング、この人はどういう人かというプロファイリングをされて、言わばそのつなげることによってその人の全情報、全人格が、今やもう人格までプロファイリングできますから、人格まで掌握されるということがこの問題の最大の問題なわけであります。それに顔認証とか生体認証まで加わると、町にセンサーですね、カメラというよりも、監視カメラというよりもセンサーが付いて、それぞれのスマホとかと一緒になって行動、行動軌跡まで追いかけられるとなるようなことがいいのかどうかということを問題提起をしているわけですね。
データの収集、嫌ならば同意しなきゃいいじゃないかというふうに答えられておりますけれども、この丸ごとシティーという考え方でいきますと、同意しないと、一つのサービスだけじゃなくていろんなサービスが連携しておりますので、サービスが受けられないということになるわけで、おのずと、おのずと自発的にといいますか、同意をせざるを得ないというふうなところに誘導する仕組みになっているということであります。
そこで、プライバシーの方が大丈夫かということが今日も議論があったわけでありますけれども、答弁は、個人情報保護法制を守る、個人の同意を得てやりますの繰り返しであります。同じことばっかり言っておられます。
今、この個人情報で何が問題になっているかというと、勝手に分析される、特に今は個人情報保護法が議論になっている最中ですけど、一番はクッキーですよね。御存じだと思いますけど、クッキーというのは、インターネットとかで検索したり閲覧したりその履歴が一時的に残る、あるいはパスワードがまた使えるというのは、そのクッキーが保存する役割しているわけですね。これは匿名なんですよね、匿名なんです。名前分からないんです。
ところが、そのクッキーの情報、クッキーがほかの情報と符合されると、その人が特定できるというところまで今技術が進展していて、それがこの間のEUの保護法制のGDPRとか、アメリカのカリフォルニアの規制とか、あるいは日本の今回の個人情報保護法の改正の目指すところは、そのクッキーによる、匿名なのにそれが、個人が分かるようなところまで進んでいることをどう規制するかというところが今大きなテーマになっているわけですね。
ところが、GDPR、EUの方は、それに対して踏み込んだ改正をこの間やってきております。アメリカも、カリフォルニアも、そのクッキーの情報について踏み込もうとしております。ところが、今かかっております日本の個人情報保護法制の改正は、そのクッキーというのを個人情報というふうに捉えておりませんので、そこのところがもう不十分というか、前よりは規制の方向なんですけれど、とても追い付いていない状況なんですよね。
申し上げたいことは、最先端技術はどんどんどんどん進化していて、それを世界中の保護法制が、個人情報の保護法制が追いかけているんですけれど、ずっと後追いになっているんですよ。日本は特に遅れているわけですね。そのときに、この世界にどこにもないようなこんな丸ごと情報都市、スーパーシティをつくろう、言わば、先進国で一番個人情報保護が遅れている日本で、先進国で一番緩いこういう丸ごと情報管理社会をつくろうとされているということの恐ろしさ、危険性、これをよくよくお考えになるべきだというふうに思うんですね。
だから、要するに、その個人情報保護法制守りますと、個人の同意を得てと何度もおっしゃいますけど、それを、それがもう現実に追い付いていないんです。それを守っても、今ある遅れたものを守っても守れない世界が来ているんですよ。そういう認識をまずお持ちでしょうか。
○政府参考人(村上敬亮君)
お答え申し上げます。
懇談会の構想時点でも、その当時の専門家の御意見の、方々でいえば、リベラルなオーダーの中で住民の合意を取りながらどのように使っていくかというようなことで、住民のデータの取扱いも含めてそこをしっかりと議論していくということは極めて重要な課題であると認識をされております。
また、プロファイリング等々データの一元化の議論ございましたが、構想段階ではそのような用途をそもそも考えていなかったので報告書の中では余り触れられておりませんけれども、私ども御説明申し上げているとおり、データ連携基盤でもできるだけデータの一元的管理を行わないと。必要なときに必要なデータの連携、共有を進めるような形にすることで、そういったような懸念をできるだけ、そもそも回避できるような方向性でシステムを考えたいと考えてございます。
個人情報保護、在り方一般、全体については私の立場から十分不十分を申し述べることは避けたいと思いますけれども、いずれにせよ、我が国の個人情報保護法制にはしっかりと従った形で、データ連携基盤整備事業者もサービス事業者もこれらの対応の中できちっとやっていただきたいと、このように考えているところでございます。
○大門実紀史君 このお配りいたしました内閣府の戦略特区のスーパーシティの資料ですけど、これ、こういう世界というのが私が申し上げた世界であって、今おっしゃったように一個一個守っていくということなら、これ実現できません、できません。
具体的にちょっとお聞きいたしますけれども、資料の二枚目の下の方に、中国の杭州、これがしょっちゅう出てくるんですよね、今回の話で。片山さんもこの中国の杭州すごいすごいとおっしゃっていましたけれども、この杭州の一体どこがすごいんですか。説明してくれますか。
○政府参考人(村上敬亮君)
お答え申し上げます。
片山先生も若干おっしゃられておりましたが、既に二千台以上のサーバーと四千台以上のカメラという膨大な端末をしっかりと渋滞管理や救急車両通行の円滑化などにきっちりと使えて運行実績があると。これだけの膨大なシステムを都市管理できちっと動かしているというところの技術的な先進性というんでしょうか、実績性というんでしょうか、その現場を見たいという思いで私自身も調査団の一員として杭州に行かせて、参りました。
正直、そこで取得されたデータを中国政府がどのようにお使いになられているかは我々の関心の対象外でしたので特段調べてこられませんでしたが、やはりこのような使用実績のある技術、要素技術では決して日本のIT負けていないと思いますが、やはり実際に使い込まれているかどうかというところで海外に先んじられますと、日本がいざそれを必要とする段階になったときに、気が付くと全部海外の技術しか使うものがないということになりかねないのではないかという意味でも、技術がスマートシティーの中で使い込まれている現場でその実態と様子を見たいということで杭州に行ってまいりました。そうした技術的先進性に着目をして、杭州については調べさせていただいているところでございます。
○大門実紀史君 これだけじゃなくて、村上さん、あれですかね、この新書、出たばかりですけど、「幸福な監視国家・中国」という本、読まれましたですかね。事務方は読んでいたと言います、読まれたと思うんですけど、すごい社会なんですよね、今、中国は。ございましたように、もう何万台というカメラが町じゅうにあって、しかも、日本の隠しカメラみたいにひっそりと映すんじゃなくて、堂々と映してあんたを見ているぞというような世界ですよね。しかも、生体認証から何から、中国の国民は自ら、自分でアプリで自分の健康データから何かを全部自分から提供すると、で、その分サービスを受けるということで、まあすごい、ある意味ではすごい監視社会でもあるわけですけど、資料の、そういう面が、サービスだけじゃなくて、いざ何かあると、東京新聞にございますけれども、反体制の人をすぐ摘発できると。民主主義、言論を弾圧できるということにも使われる表裏一体な仕組みなわけでありまして、技術が遅れているとおっしゃいますけど、遅れてはいけない技術と遅れてもいい技術というのもあるんですよね。だから、何か中国だ中国だというの、ちょっとこんな社会を目指すのかということは考えなきゃいけないと思います。
中国は、何というんですかね、国家資本主義みたいなものでございまして、独裁国家でありますから、そういうところが好き放題にやっていることを、すごいすごいといってこうやって日本の国会の資料にこんな喜んで紹介するのかなと、私は非常に疑問です。
もちろんこれ、アメリカでもペンタゴンがかつて学生のメールを勝手に、反体制の学生いないかとやったことありますから、中国だけに限らないのかも分かりませんが、こういうことについてよく考えないでこんなものモデルにする必要ないなというふうに思うわけでありますけど。
去年の八月三十日に、片山さんおられたら直接聞きたいぐらいなんですけど、片山さつき前大臣が中国の国家発展改革委員会のトップと、地方創生に関する日中両国の協力を強化すると、地方創生で協力するという覚書を交わされました、片山さつき前大臣が去年の八月ですね。
これは何のために交わした覚書ですか。
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。
御指摘の地方創生の協力の推進に関する覚書は、片山大臣、当時御自らも中国に赴き現地調査を行った際に、中国政府幹部と二国間で対話をしていた際に、先方の幹部との間で協定締結の話題があり、その後、協議を経て二〇一九年八月三十日に締結したものでございます。
この協定につきまして書かれていることは、基本的には窓口を内閣府地方創生推進事務局と中国国家発展改革委員会の担当部局の間とすると、その間で定期的に協議をするということで、何を協力内容とするかはこれから議論しましょうということになっていたところ、今回のような状況でその協議自身が現状一部、一時中断をしてございますので、その協力内容の具体化については今後正常化を待った上で中国政府側とまた相談をすると、こういう状況でございます。
○大門実紀史君 これ、ほかの国とこういう覚書交わしていないですよね。中国だけですよね。
なぜ中国だけと、中身はこれからにしろ、地方創生とかこういうものについて中国と特に交わす必要があったのかと。
それで、私、手元にそのときの覚書がありますけれど、何が書いてあるかというと、もちろんこれからだということはあるんですけど、双方は、日中両国のモデル地区、日本はスーパーシティ、中国は国家級新区、新しい区、国家級新区に関する相互理解の重要性を認識し、今後の在り方について協議していくことで一致したと。
なぜ中国とこれを協議する必要があるのかと、日本のスーパーシティをですね、大変な疑問があるわけですけど、今のところ、やろうと思ったことをやれない段階なので、いろいろ答えられないと思いますが、そのときの記者会見で片山さんは何をおっしゃっているかというと、要するに先ほどの話ですね、日本はこういう点ではIT、デジタル技術は中国に遅れていると、我々としては日本中の地方の「むらの宝」を中国に積極的に売りたいと、日本の特産物、農産物等々ですかね、輸出をしたいと、インバウンドでも来てほしいと、で、お互い、国家戦略特区とか云々とあるんですけれど、そういう関係を続けたいと。
よく考えてみると、このスーパーシティ構想に関わりますビッグデータを扱うノウハウ、ITの最先端の技術というのは、今持っているのは、日本単独では無理ですね。もう認めておられるとおり遅れています。海外の大手IT企業の力を借りるしか、このスーパーシティも実際にはいろいろやれないということになると思います。
それを考えますと、今それがやれるのは、連携してやれるのはアメリカのGAFAですね。特にグーグルではないかと、想定されるのは。もう一つは中国のBATHですね。BATHですね。アリババ、何だ、ファーウェイか、とか幾つかありますよね、それをまとめたのがBATHという言い方するんですが、特にアリババではないかと、ですよね。
つまり、わざわざ中国とこういう覚書を結ぶというのは、当然中国からはそのIT技術を提供してもらって連携していくと。杭州はアリババがやっていますよね。トロントはグーグルですよね。だから、そういうIT大企業の力を借りて日本でもやる。その点でいくと、中国との連携を視野に入れた覚書ということではなかったんですか。
○政府参考人(村上敬亮君)
お答え申し上げます。
御指摘をいただいた技術的知見における専門家間での知見の交流ということは少なくともあるだろうと。中国と、たまたま経緯で最初に中国ということになりましたが、地方創生でいきますと、韓国とも結んでおりますし、本来私ども、インド、イスラエル、欧米、全てやりたいということで動いておりましたんですけれども、残念ながらちょっとそこまで私どもの手が及ばなかったというのが経緯論としては実態でございます。
連携をどこまで考えているかという点でございますけれども、これも当時の経緯でいいますと、特に中国側が第三国に対していろいろな協力をしていくときに一緒にやりませんかというアジェンダをいただいておりまして、内容次第とは思いつつも、彼らのテクノロジーをマレーシアが実際に購入するしないといったような話も当時あったものですから、そういったような形での連携をすることはあるかもしれないという議論にはなっておりましたけれども、結局のところ、どういう協力内容とするかは、議論が中断しているので、今後検討するというような状況でございます。
○大門実紀史君 実は、竹中平蔵さんの、いろんなところ、大阪でのシンポジウムを含めて有識者会議の発言、ほとんど読みましたけど、そこに中国が何度も出てくるんですね。ですから、中国のIT技術と連携して日本のスーパーシティという一つの選択、少なくとも一つの選択肢ではあるんではないかというふうに思います。
その点で申し上げたいのは、技術というものとどういう社会を目指すのか、どういう社会であるべきかということは表裏一体でありまして、先ほど申し上げましたけれど、アメリカは、GAFAに見られるように、民間主導で、分散型の競争でやってまいりましたよね。中国の場合は、先ほど申した国家資本主義といいますか、官民で一体となってこの技術開発を、もちろん中国の中でも競争させるわけですけれども、全体としては一体となってきたわけでありまして、そういう、しかも、中国の場合は本当に民主主義を抑圧して、一党独裁の国でありますから、そういう国が一生懸命開発した技術と、後で申し上げますけれど、これからの技術の在り方なんですけれど、分散型の個人のプライバシーを守る技術の在り方というのはおのずと違うわけですよね。
ですから、そういう技術の在り方も含めてもうちょっと、何といいますかね、本当にもっと深く考えた分析をして、IT、これからのスーパーシティ考えないと、中国のそんな変な技術を学ぶ必要はないんですよね。もっとこれからの、プライバシーと両立するような、その技術ってまたあるんですよね。それを、そういう点では大変心配な方向に今行っているんではないかと思います。
その点で、日本でもしも最先端技術を取り入れた町づくりを考える場合、参考になる国とか町がほかにないのかというと、私は、これはもちろん政府の資料にも載っておりましたが、バルセロナではないかと一つ思っております。
時間の関係でこちらで簡単に言いますけど、トロントは、前回も指摘させてもらったように、住民の反対運動がたくさん起きて、結局頓挫してしまいました。財政の問題もありますけれどね。なぜ起きたかというと、やっぱり民間企業、グーグルが個人データをこれ握るというところに対する反発とか、住民ときちっと話をしてこなかったというのがあるわけですね。ところが、スペインのバルセロナの場合は、長い間掛けて住民との話合い、そのセンシティブなところはもう触れないと。そういうデータをやるんじゃなくて、本当の、交通の、みんなが喜ぶことだけに技術を生かしましょうということでやっているので反発がないんですよね。
何が重要かというと、今日も御議論ございましたけど、森ゆうこさんとか福島さんからありましたけど、その住民合意の在り方が今回担保されていないと。だから、このまま行くとバルセロナじゃなくてトロントになってしまいますよということなんです。
先ほどありました区域会議に、今のところ、これ区域会議というのは特区担当大臣、首長、事業者ですよね。これだけで構成するんじゃなくて、この構成の中に、選び方はいろいろあるかと思いますが、住民代表を必ず入れると、区域会議の中に入ってもらうということをやるだけで、いろんなプライバシーの問題とか心配されている問題が、しかも話合い、時間掛かってもいいと思うんですよね。そういうことに資するようなことをやっぱり考える必要があるのではないかと思うんです。
竹中平蔵さんが有識者会議でこんなことを言っているんですね、グリーンフィールドがいいと。つまり、何もないところに新しい町をつくった方が住民の抵抗が少ないと、そういう言い方をされているんですね。つまり、新しい町つくって、サービス、監視社会だけどサービスしますと、それでよければ住んでくださいということだったら、それは住みたいというところで住民合意取りますから、それが一番いいやり方だと、抵抗のないやり方だと。今までにある町に導入すると抵抗が起きるというようなことをおっしゃっていて、個々に表れている住民の主権とか住民合意を無視するような発想で、このスーパーシティというのは構想が練られてきたんじゃないかと思うわけであります。
逆に、グリーンフィールドで新しい町にそういうものをつくったとしても、最初は、分かりましたと、このサービスならプライバシー、自分の情報を提供しますと入居されて移ってこられたとしても、どんどん進化しますよね。その途中で、やっぱりこのサービスでは嫌ですと、そうしたらそこから出ていけるのかと、ほかの町に住みますって出ていけるのかと、できないですよね。
そういうことも考えると、住民の合意とかそういうものはずうっと確保されなければいけないものだというようなことも含めて、もっともっと深く考えなきゃいけない点でいくと、森ゆうこさんや福島さんからあったとおり、もうこれ欠陥法案ですね。かえってこんなことを進めると大反対運動があちこちで起きて結局実現できないというような欠陥法案ですから、本当にもうこれ撤回した方がいいですよ。もう一遍考え直した方がいいと思いますよね。大臣、うなずいておられますけど、本当に考え直した方がいいということを申し上げておきたいと思います。
一応、参考までに配りましたので、資料の六枚目は、資料の六枚目はこの前申し上げたハラリさんのやつです。七枚目はデビッド・ライアンさんの監視文化です。最後は、先ほど申し上げましたそういう監視社会じゃなくて、データとプライバシー両立するようなことを考えるのが日本企業のこれからの在り方だということを田中道昭さんが提案されておりますので、こういうものをきちっと読んでもう一遍この法案は出し直すということを求めて、私の質問を終わります。