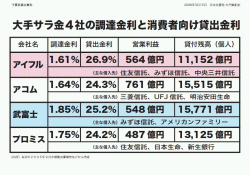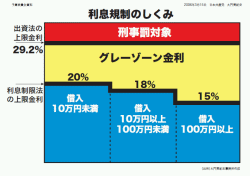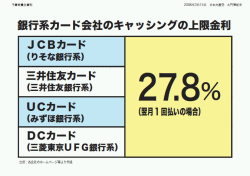| ■2006年3月15日 予算委員会(一般及び証券・金融集中審議) サラ金の暴利正せ、金融担当相も「CM不愉快」 | ||||||||
| (午前の部) ○大門実紀史君 日本共産党の大門でございます。 今日は、午前午後を通じて、サラ金、クレジットの高金利、高過ぎる金利について取り上げたいと思います。 この間、多重債務、自己破産あるいは自殺ということで、やみ金だけではなくてサラ金、クレジット被害の問題も社会問題化しているところでございますけれども、こういう中、最高裁がこの間相次いで、いわゆるグレーゾーンの撤廃に向けた、そういう方向の判決、あるいは高金利を引き下げる、を促すような方向の判決を出してきているところでございますけれども。 まず金融庁に伺います。いわゆる上限金利のグレーゾーンの存在がいろいろ引き起こしてきたわけですけれども、このグレーゾーンそのものについて分かりやすく説明をしていただけますか。 ○政府参考人(三國谷勝範君) お答え申し上げます。 いわゆるグレーゾーン金利でございますが、これは一般的に、刑事上の上限金利を定めました出資法と民事上の上限金利を定めました利息制限法、この二つのそれぞれの上限金利の間の金利を指すものとされていると承知しております。 なお、貸金業規制法四十三条一項におきましては、いわゆるグレーゾーン金利に当たります利息の支払につきまして、一つは債務者が利息として任意に支払ったこと、二つは契約締結時及び弁済受領時の書面を交付していること、この二つを要件として有効な弁済とみなすこととされているところでございます。 ○大門実紀史君 ありがとうございます。 与謝野大臣に伺いますけれども、なぜ日本にこういうグレーゾーンが今まで存在してきたのか、どういうふうに思われますか。 ○国務大臣(与謝野馨君) これは、出資法と利息制限法という二つの法律があって、貸金業者は利息制限法で規制されているわけでございますが、出資法ではそれより高い制限が掛かっているわけでございます。その際、これらの法律を改正するときも、二十年近く前だったと思いますけど、いろいろ議論があって、それではそのグレーゾーンについては契約のときの任意性とかあるいは支払のときの任意性とかということが条件でそれでは認めようと、そういう経緯があったというふうに覚えております。 ○大門実紀史君 もう少しリアルな経過、調べてみましたので申し上げますと、いわゆる八三年のサラ金二法ですね、貸金業規制法と出資法が成立したときですけれども、これは当時から議員立法でございました。この議員立法の提案者の大原一三議員がこういうふうに国会でも発言されています。これは初めて貸金業者に規制を掛ける法律だと、それをのませるためのあめとして、あめとしてこのグレーゾーンを設けたんだと言っております。当時の新聞も調べてみましたけれども、八三年四月二十八日に法律成立したんですけれども、三十日の新聞には、もう業界が大喜びの、業界にとっての悲願だったと、この法律の成立はというふうに、大変業界が歓迎して、逆に、サラ金被害に遭った人たちの弁護士さんとか団体は、これじゃ何が一歩前進だというふうに言っていたわけです。 つまり、経過とその後の事実からしても、この貸金業規制法、議員立法でやられたものは、今のグレーゾーンの被害につながるものをつくってしまった。そして、逆に言えば、今のサラ金業界、もう世界で類のない発展を、急成長ですけども、そういうものをつくってしまった背景にこの八三年の立法があり、グレーゾーンの設定があったというふうに言えると思います。 私はそもそも、これは法務大臣にお聞きしたいんですが、出資法や利息制限法のことですから、議員立法じゃなくって政府、法務省が提案すべきだったものだと思いますが、いかがですか。 ○国務大臣(杉浦正健君) いや、べきであるとかべきでないとかは別にして、法律は国会がお決めになることでございますから、議員提案であって、それに政府が協力をして制定されるに至ったと承知しております。 ○大門実紀史君 御存じなければお教えしますけども、一九六四年に、あるいは六八年に最高裁判決が出ておりました。つまり、もう利息制限法以上は駄目だよと、民事上駄目だよという明確なすぱっとした判決が出ていたんです。で、業界団体はそれでは困るということで、適用を除外してくれと、登録したら適用を除外してくれという強い要求をしておりました。それで、八三年にこういう適用除外とみなし弁済のグレーゾーンを認めてあげるというふうになったわけですね。 このときに、当時自民党のサラ金小委員でした藤井裕久さん、こうおっしゃっています。これは、最高裁の趣旨を割り引くような、骨抜きにするような法改正は内閣とか法制局とかはできないと、だから議員立法でやってもらったんだと。もう逆に言えば、その最高裁の判決どおりやるつもりだったらば内閣でも法務省でも提案できたというふうに私は思います。いかがですか。 ○国務大臣(杉浦正健君) 当時の事情は承知しておりませんが、重ねて申しますけれども、議員提案であろうと内閣提出であろうと、法律案は国会で審議されるべきものでございます。 ただ、法務省の場合は、最高裁判所の判断があれば、それは尊重しなければならないということはあり得ると思います。 ○大門実紀史君 私は、議員立法一般を否定するわけではございません。活性化すべきだと思いますが、こういう議員立法はちょっと問題ではないかと思って質問しているわけですけども。 今おっしゃいましたんで聞きますけども、そうしたら、早い話、今回も最高裁判決が出て、グレーゾーンを撤廃する方向で考えろとなっております。法務省の所管ですから、すぱっと出資法の上限を利息制限法に下げるという提案を、最高裁判決どおりやるんでしたら、提案されたらいかがですか。 ○国務大臣(杉浦正健君) 私は、この平成十五年のやみ金融対策法には議員の一人でかかわっておりましたのでその経緯は承知しておりますが、当時、もうやみ金融がはびこっておると。上限金利を超える、何倍もの金利を取って庶民を苦しめているやみ金融をいかに退治するかという点に一つの焦点を置いて議員立法であのやみ金融対策法を作ったわけでございますが、国会は通ったわけですが、その法律には、施行後三年、すなわち平成十九年一月を目途として所要の検討を加え、必要な見直しを行うものとされております。 最高裁の判例は、そのグレーゾーンについて、任意性その他について厳しい判断をされておるわけですが、グレーゾーンそのものを否定されているとは私は考えておりませんが、上限金利の在り方については、資金需要の状況、金融業者にも悪いのと良心的にやっている人がおられます、資金需要の状況、その他の経済・金融情勢や貸金業者の業務の実態等を勘案して検討する必要がございます。 今後とも、関係機関と協力しながら必要な検討を行ってまいりたいと思っております。 ○大門実紀史君 せっかくいろいろ申し上げたのにお分かりになっていないようでございますけども、続きは午後の第二ラウンドでやりたいというふうに思います。 ありがとうございました。 ○委員長(小野清子君) 以上で大門実紀史君の質疑は終了いたしました。(拍手) (午後の部) ○委員長(小野清子君) 次に、大門実紀史君の質疑を行います。大門実紀史君。 ○大門実紀史君 日本共産党の大門実紀史でございます。簡潔な答弁をお願いしたいと思います。 午前中に続いて、サラ金、クレジットあるいは銀行カードの高過ぎる利息、高金利の問題を取り上げたいと思います。 多重債務や異常な高金利による自己破産、自殺というのがマスコミでも取り上げられてきているところでございますけれども、消費者金融白書によりますと、これはもう一部の人の問題ではございませんで、この消費者金融の利用者は働く人の四人に一人になっていると。約二千万人が利用している問題です。そのうち多重債務に陥っている人が二百万人、毎年二十万人が自己破産をしているという大変な問題でございます。 この白書によりますと、借り手の平均年収は約四百五十万円と言われています。中堅所得以下で生活に余裕のない層が銀行から借りられなくて、こういうサラ金に高い金利を払わされているのが今の実態でございます。一方、サラ金各社は、報道されているとおり、莫大な利益を上げておりまして、また高額所得者のトップクラスにサラ金の社長とその親族が名を連ねるという、そういうことも起きております。 ただ、この間、最高裁が相次いでこういう高金利引下げを促す判決を出しておりまして、法律の改正も今求められているところでございます。どれだけ高い金利かということをまず見てもらいたいと思います。(資料提示)
調達金利わずか一%台で調達したお金を、貸出し金利二十数%で貸していると。もう暴利と言ってもいいと私は思います。それで営業利益を、これ半期ですけれども、これだけ稼ぎ出しているわけでございます。しかも、主な借入れ先というふうに書いてありますけれども、ほとんどが大銀行グループでございます。中にはアメリカも入っていますし、ちゃっかり新生銀行までこういうところに顔を出しているわけでございます。 与謝野大臣にお聞きいたしますけれども、なぜこういう異常な高金利が日本では許されているんでしょうか。 ○国務大臣(与謝野馨君) 貸金業者の金利につきましては、刑事上の上限金利を定めた出資法、民事上の上限金利を定めた利息制限法等により規制はされております。 貸金業者の貸出し金利の水準や、いわゆるグレーゾーン金利問題を含む金利規制の在り方など、貸金業制度等をめぐる諸問題については、現在、貸金業制度等に関する懇談会において勉強をしているところでございまして、引き続き議論を深めてまいりたいと、そのように思っております。 ○大門実紀史君 今お話ありましたグレーゾーンということが許されてきたからでございます。
今、出資法の上限金利は二九・二%です。利息制限法の上限金利が、借りる額によって変わりますが、一五%から二〇%でございます。この間をグレーゾーン金利と申します。で、グレーゾーン金利というのは、本来、利息制限法からすると無効な金利の設定でございますけれども、ただ、本人が任意にその利息を払うということを言えばこの金利を取っていいということになっておりますが、実際問題、借り手の弱みに付け込んでこのグレーゾーンの範囲の高い利息を押し付けているのが今の実態でございます。これが今問題になっていて、最高裁も、このグレーゾーンの金利を取る場合はよほど厳格に本人の任意性を確認しなければならないと、そういう判決を今出しているところでございます。
これは大手銀行系のキャッシングのカードローンでございますけれども、何とサラ金よりも高い二七・八%という利息を取っております。ですから、サラ金問題だけではなくて、このカードローンの問題、これも今問われているというところになります。これは、グレーゾーンがあるんで、それをいいことにこういう二七・八%という高金利を取っているわけでございます。 もう一つ銀行の問題でどうしても触れなきゃいけないのは、これは新聞広告でございまして、(資料提示)今や銀行とサラ金会社が一体になってこういう個人向けの消費者金融に乗り込んできているというこれは新聞広告で、朝日新聞の新聞広告でございます。三井住友はプロミスを傘下に入れているんですね。しかも、先ほど言ったように資金を提供して、リスクの低いところ、つまり優良なお客は三井住友でカードで貸すと。リスクが高くなればアットローンで貸す、更に高ければサラ金のプロミスに回すと。こういうことが、もう大手の銀行戦略としてリテールの中でずっと行われているわけでございます。 私は、これでいきますと個人情報も、銀行の預金者の個人情報もどうなっているのかということを非常に心配いたしますが、これ三井住友だけではございません、ほかの大銀行もこういうサラ金との提携に今ずっと進んでいるところでございます。 一言言っておきますけれども、この写真の女優の木村佳乃さんには罪はございません。私もファンでございますけれども、こういう方のイメージを使って、イメージを使って安心させると。銀行の信用ブランドを出して、で、サラ金のノウハウを使ってこういうことが行われているということでございまして、私は異常な事態が進んでいると思います。 先ほどから量的緩和の話がありましたけれども、日銀がじゃぶじゃぶにですね、じゃぶじゃぶに銀行に回したお金がこんなことに使われていると。これは与謝野大臣、いかが思われますか。 ○国務大臣(与謝野馨君) 近ごろ不愉快なことは、やはりテレビコマーシャルにそういう高い金利で貸すサラ金業者の広告が堂々と載っていることと、かつては私は超一流銀行だと思っていた銀行がサラ金業者と一緒に広告を出しているというのは、私の気持ちとしては、最近不愉快のことの一つでございます。 ○大門実紀史君 ありがとうございます。これからこういう広告がなくなればいいというふうに思います。 この最高裁の判決を受けて、グレーゾーンの見直しが、法改正が求められることになってまいりました。この法改正は議員立法で提案することになるようでございます。私、議員立法一般は国会議員の仕事として活発にやるべきだという考え方ですが、この議員立法については大変危惧を抱いております。 なぜなら、午前中も指摘いたしましたけれども、この議員立法、最初から、貸金業法規制法ですけれども、議員立法ですが、八三年の制定ですね。そのとき、その者が、そのときの提案者自身が、これは業界向けに、業界に向けたあめだと、業界に向けたプレゼントだと。そんなことをしちゃってできたのがこのグレーゾーンで、それによって日本の貸金業が世界で類を見ないほど巨大産業になってしまったと、サラ金がですね。そういうことになっているわけで、たくさんの人がまた苦しんでいるのもそのせいだと思います。 今回も、貸金業界は金利の引下げに強い危機感を抱いております。貸金業団体の政治団体、全政連というのがございます。これは全国貸金業政治連盟でございますけれども、与党の議員の皆さんに働き掛けを活発化しているようでございます。この組織は元々、この貸金業法が議員立法であるということを想定して、議員立法に向けて取り組むことを目的としてつくられた政治連盟でございまして、例えば全政連の第五回定時総会議案書にはこういうふうに書かれています、これ去年の五月ですけれども。当連盟は政治団体として貸金業界と議員立法を担う国会議員とのパイプを築き、それを盤石なものとしていく役割を担っていると。創立以来の活動によって、与党議員連盟を始め多くの議員が業界に理解を示してくれて、要望を国政に展開させる環境は整ったのであると。これは実は今回の見直しに向けての発言でございます。 今回も、利息の上限を下げないような議員立法を求めて活動しておりますけれども、もしもその議員立法が、こういう一部の団体から献金を受けたり、あるいはパーティー券を買ってもらっている議員が中心になって業界に有利な議員立法を作るということになると、私は大変だというふうに思います。与党が、もし与党が作った議員立法でしたら数の上から実現可能性高いわけですから、そんなことで作られたら大変だという認識を持っているところでございます。 自民党の中には、金融サービス制度を検討する会という議員連盟がございます。〇五年四月に再開といいますか、できたわけですけれども、その三か月前の一月に、先ほど言いました全政連の名誉会長である小倉利夫貸金業団体の会長は、日本金融新聞の中でこんなことを言っています。全政連では議員の方とパーティー券購入などのお付き合いをしているが、前回の法改正と同様に、前回の法改正と同様に議員連盟をつくってほしいと、何人かの議員にはお願いをしていると。先ほど言いました議員連盟ができる、金融サービス制度を検討する会ができる三か月前の発言でございます。そして、四月にできたということでありますので、私は、この全政連の働き掛けが強く働いたんではないかというふうに思っておりますし、以来、何度も全政連のメンバーとこの自民党の議員連盟が懇談をされております。 ちなみに、この議員連盟、参加されているのはほとんど衆議院議員の皆さんで、参議院の皆さん余りおられませんですけれども、小倉会長はここで言っている、何人かの議員とつくってもらうように、議員連盟をつくってもらうように頼んだ何人かの議員とはだれかというふうに私は思います。 そういうことで議員連盟つくって議員立法作っていいのかなというふうに思うわけでございまして、最近、この議員連盟の中心メンバーによって更に一応超党派という形の金融システム整備による経済活性化を推進する議員連盟というのが呼び掛けられました。高金利引下げの一文字もない議員連盟でございます。我が党にもいったん話がございましたけれども、やはり共産党は入れない方がいいというふうなことらしいでしたけれども、もう上等でございまして、こちらの方からお断りでございますけれども。 全政連はこの議員連盟にも大きな期待を寄せているわけでございまして、率直に申し上げます。サラ金被害に苦しんでいる人たち、消費者団体の人たち、弁護士さん、戦ってきた弁護士さんの人たちは、この議員連盟の動きあるいは中心になっている与党議員の動きに非常に心配されております。前回のように、業界寄りの投書とか業界に譲歩したものが出てきて、せっかくの最高裁の判決があって高金利引下げのチャンスなのに、それが業界寄りにぶれてしまうことを大変心配されているところでございます。 我が党は、こういう議員の方々の動きについて調査をいたしました。各県の貸金業業界、貸金業団体の顧問になっている方、あるいは全政連に三年間続けてパーティー券を買ってもらっている方などおられます。さらに、ある議員は、事もあろうに引き下げるんじゃなくって出資法を引き上げると、そんなことを言っているということまで全部調べました。 今日は武士の情けで名前は言いませんですけれども、これから何をされるかが問題でございますから、名前を伏せておきますけれども、要するに、私、一般論として、議員が、国会議員が特定の団体から献金受けたり、パーティー券買ってもらって政府に国会質問をしても、今や受託収賄罪に問われる例もあるぐらいでございます。ましてや、自ら議員立法の立法をすると、特定の団体からですね、そういう関係がある人がですね。私は、それ非常にもう大変なことだと、質問して受託収賄罪に問われた方いるわけですからね。それよりも、自ら法律作るとなると、これは大変なことだというふうに思います。 最後に、総理にお聞きしたいんですけれども、これは本当に被害を受けてきた方とかの高金利引下げはもう本当に切望されていることで、弁護士さんたちも頑張ってこられましたし、国民のこの高金利引下げに対する要望はもう強いものがあると思います。私は、国会の責任として、むしろ超党派で本当にどうやって利息制限法に持っていくかという議論をして、真っすぐに最高裁の判決にこたえるのが国会の仕事だと思いますが、総理のお考えをお聞きしたいと思います。 ○内閣総理大臣(小泉純一郎君) この問題は党派を超えて、わずかなお金を借りて多額の借金を返さなきゃいけないという、高金利むさぼっている業者、これに被害を受けないような対策を講じなきゃならないと思っております。 ○大門実紀史君 ありがとうございました。終わります。 ○委員長(小野清子君) 以上で大門実紀史君の質疑は終了いたしました。(拍手) |
||||||||
| 戻る▲ |